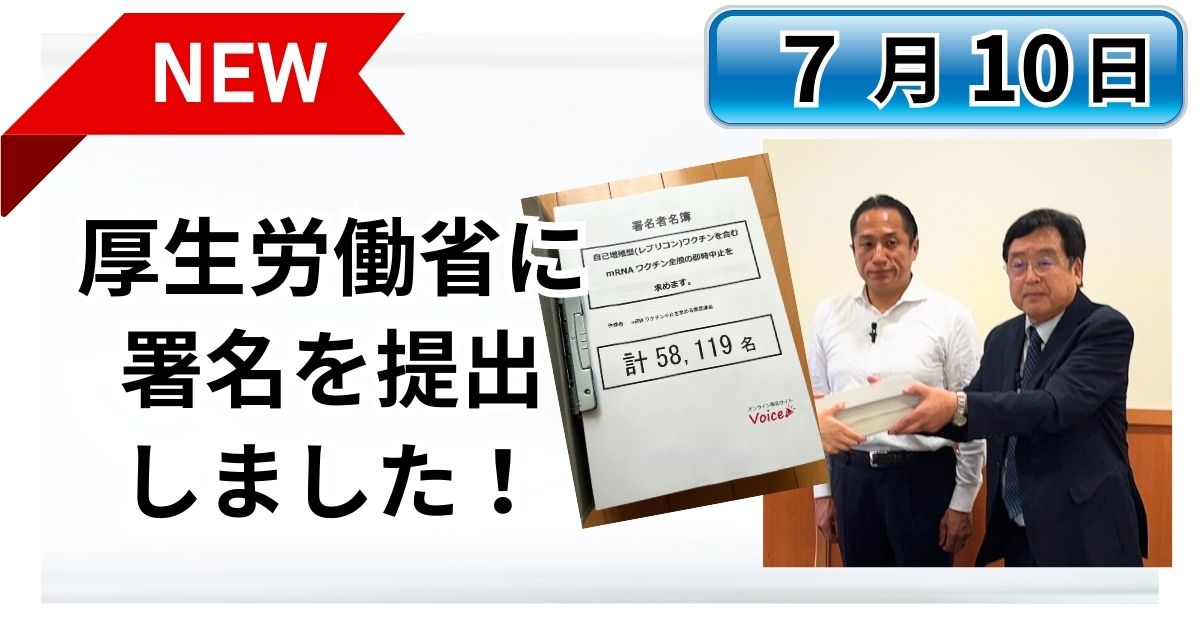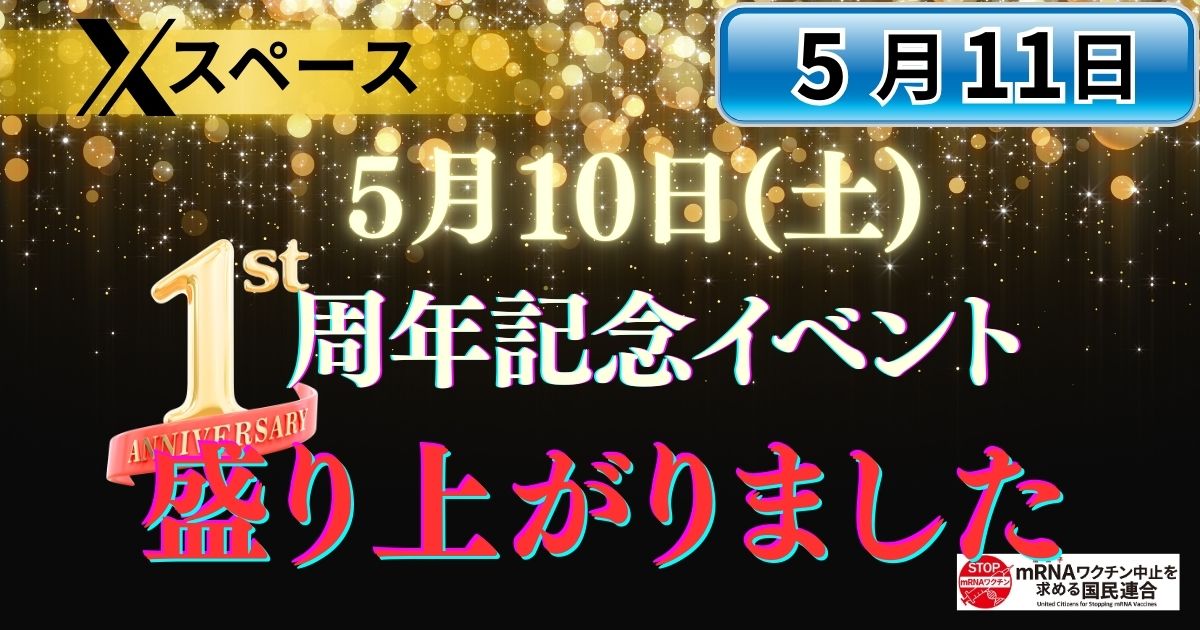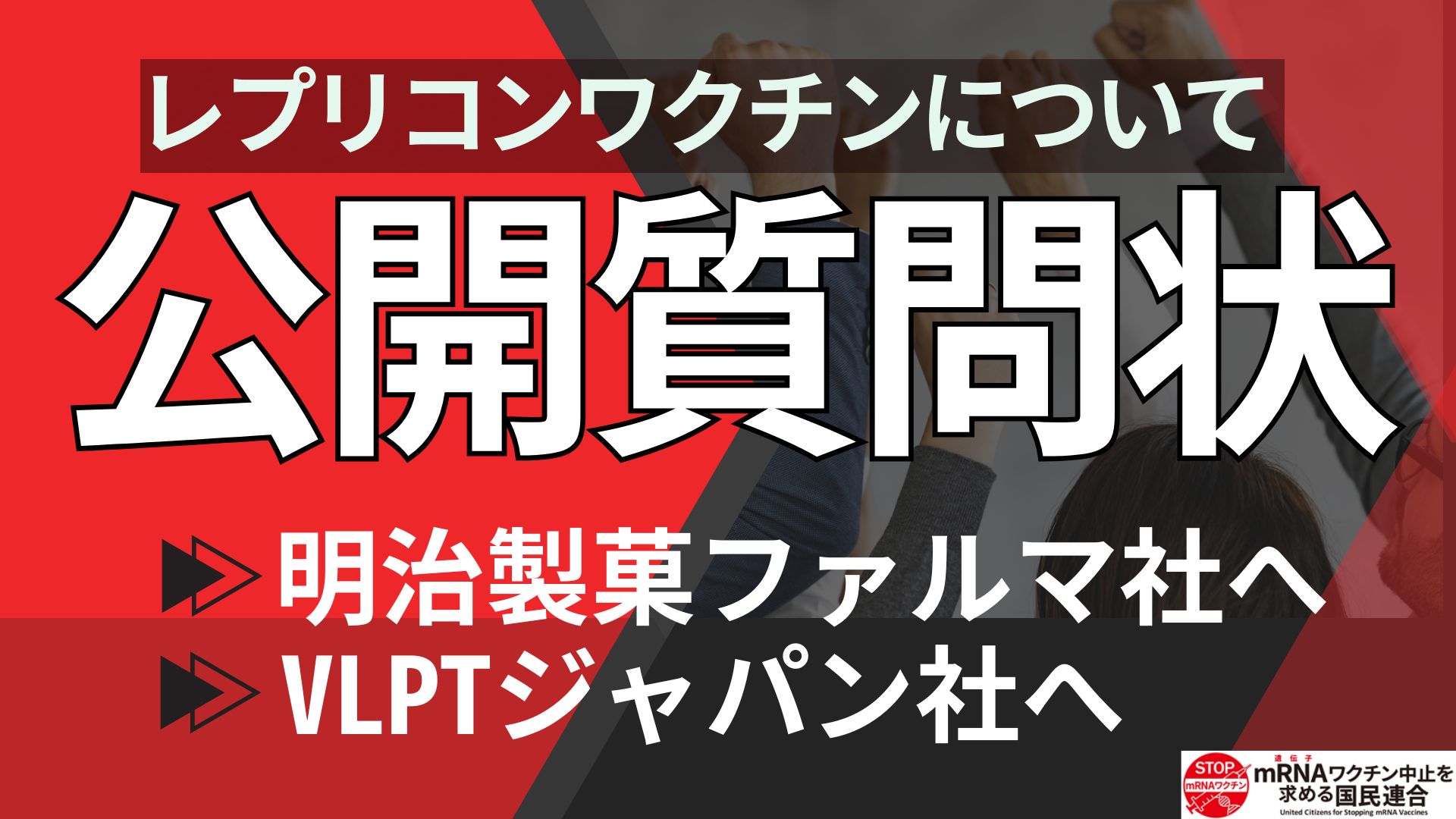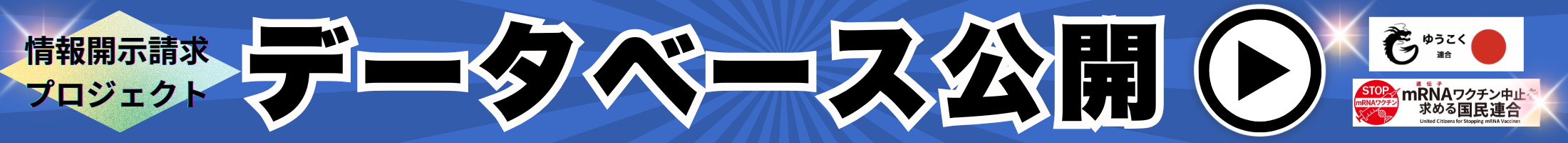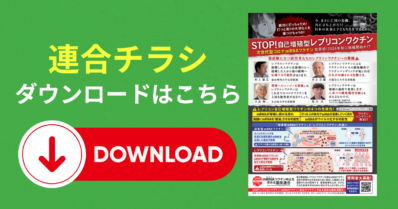2025年9月に東京理科大学新田剛教授らが発表したプレプリントに対する見解
mRNAワクチン中止を求める国民連合
著者らは現在下記のプレプリントを自らSNS上などで発信拡散している。
Verification of questionable information about the COVID-19 vaccines.
COVID-19ワクチンに関する疑わしい情報の検証
JXiv preprint. (Nitta, Kashiyama et al. 2025)
https://jxiv.jst.go.jp/index.php/jxiv/preprint/view/1428
著者: 新田 剛、 樫山拓 、松本義久、豊田 哲也 、宮沢 孝幸 、 上島 (堀内 ) 由香里、掛谷英紀(敬称略 )
しかし、その内容はレプリコンワクチン (自己増幅mRNAワクチン) を含むmRNAワクチンの危険性について、専門知識のない一般の方の理解を誤誘導する恐れがある。すでにSNS上では藤川賢治氏 (小金井市議会議員) らにより十分なコメントが付されており、多くの問題が指摘され評価は定まりつつある。我々は、藤川氏と同様に、当該プレプリントがいくつかの観点から看過できない問題を含んでいるものと考え、以下に見解を示す。
(1) はじめに
新田氏らによるプレプリントでは、実験の結果、「レプリコンワクチンが接種者から非接種者に伝播する (いわゆる個体間伝播 ) は無い」、「コロナワクチンに含まれる汚染 DNAがゲノムに取り込まれる可能性について、試験管では 2%発生したが人では問題がない」と結論づけている。
Figure 1はレプリコンワクチンを投与したマウスを用いた個体間伝播の「 シェディング 」実験
Figure 2はコロナワクチン残存 DNAの測定方法の比較実験
Figure 3は DNA断片の導入実験( 細胞株 利用)である。これらに対する見解を以下に 示していく。
本来プレプリントとは、論文として評価されるだけの要件を満たし、さらに実験の結果から導出された結論が他の研究者から見ても妥当な条件を満たしているべきである。また、専門的知識のない一般の方にとっては、実験結果からは到底導き出せない結論であったり、実証プロセスに技術的な大きな問題があったとしても、それらが正しいかどうかの判断ができず、最終的な結論しか印象に残らない可能性が大きい。
著者らは当該プレプリントをSNSなどでみずから発信拡散しているが、もしそれが専門知識が乏しい一般の方に対して何らかの意図をもって印象操作を試みようとしているものであれば、研究者として非常に問題のある行為と言えよう。このような観点から、新田氏らのプレプリントの問題を指摘し、その結論に対して異議を唱え、反論する。
(2) 新田氏らのプレプリントは学術論文としての最低条件を満たしていない
実験データを主体とした学術論文には通常、Results (結果)、Discussion (考察)、Materials and Methods (材料と方法) などのセクションが必要であるが、新田氏らのプレプリントにはそれらが存在しない。とりわけMaterials and Methods (材料と方法) のセクションは重要であり、それがなければ、実験の詳細を第三者は把握することができず、その実験に対しての追試による検証も不可能となる。さらにこのプレプリントでは、実験材料の入手先や研究資金の調達先についても記載されていない。それにも関わらず、その体裁は一見すると論文に似せており、科学論文に対する知識のない者が「学術論文」として誤認しかねないものである。また、たとえ著者らが「このプレプリントが意見論文である」と主張したとしても、実験結果が提示されている以上は、実験の詳細が十分に理解でき、追試を可能とする実験条件をグラフ説明等に記載する必要がある。したがってこのプレプリントは学術論文としての最低限の要件を満たしていないと判断されて然るべきである。
著者らは、稚拙かつ粗雑な実験結果のみをもって先行研究を否定したと断言しているが、先行研究を否定するためには、その研究を質的かつ量的に上回る実験結果が必要である。
さらにこのプレプリントには、学術論文に必要な基本的な情報が記載されていないにも関わらずConclusion (結論) のセクションは存在し、著者らによる主観的な断定で締めくくられている。つまり研究論文のプロセスそのものを無視しており、結論ありきの政治的プロパガンダ資料という印象を与えかねない。このような行為は科学者に対する信頼を大きく損なうものであることは言うまでもない。
(3) 新田氏らのマウス実験のみでは、レプリコンワクチンの個体間伝播が起こり得ないことを証明できない
シェディングの解釈について
本来「ワクチンシェディング」という言葉が示す意味とは、ウイルスそのものを使った生ワクチンを打った人間が、ワクチン由来のウイルスに感染することによりウイルスを周囲に放出するという現象である。しかしmRNAワクチンの登場により、mRNAコロナワクチンの接種者から他者へ副反応が伝播する現象に対しても慣例的に「シェディング」という言葉が適用されるようになり、ここでの表記もその意味を踏襲する。
伝播が起こり得ない証明になっているのか
著者らは「自分たちの実験系の感度ではレプリコンワクチンの伝播現象を有為に検出することはできなかった」と述べている (Figure 1)。しかしマウスでの実験結果を注意深く観察すると、レプリコンワクチンの伝播により、同一ケージ内のマウスで抗体価は若干上がっているように見受けられるが、著者らはあえてこの点には触れていない。以上のことから、このような実験のみで「伝播が起こり得ない」ことを証明した、というのはあまりに論理が飛躍していると言えよう。
実験にマウスを用いる理由
実験動物としてマウスを用いることの利点には、純系が利用できること、個体差を最小限にすることなどが挙げられる。また侵襲的な手段を含め、さまざまな検体を採取できる点もヒトと比較しての大きな優位性である。加えてヒトでは倫理的および社会的に不可能な実験をも行うことが可能である。そのためマウスの実験において個体間伝播が検出されれば、実験規模の大小に関わらず明確な結論を得ることができる。
しかし当該プレプリントのように、何らかの現象の存在を否定する目的でマウスを実験に使用する場合には、相応の規模での実験が必要となる。けれども実際に新田氏らはどの程度の規模で実験を行ったのかについて実験の詳細を確認しようにも、このプレプリントには材料と方法のセクションがなく、実験に何匹のマウスが使われたのかさえ記載がない。そのため規模の把握はできないのである。このようなことは科学論文では到底考えられない不自然な行為であり、後に状況を鑑みて数量を修正するための意図的なものである可能性すら考えられる。
マウス実験の限界
一方、実験動物としてのマウスにはヒトと異なる点もある。個体差の少ない純系の実験用マウスとは異なり、ヒトでは個体差が大きい。例えば感染症では病原性因子を大量に周囲に散布するスーパースプレッダーのようなイレギュラーな人間の存在が問題となることがあるが、この点においてもマウスでは人間の持つ個人差 (個体差) の検証は難しい。
また、そもそもマウスに存在しない現象はマウスでの研究の対象外となる。コロナワクチンのシェディング現象について、「コロナワクチン非接種者の月経異常は接種者との近接と強く関連している現象」が論文でも報告されており (Peters, Newman et al. 2024)、人間の汗腺にスパイクタンパクが蓄積する症例も報告されている (Sano, Yamamoto et al. 2024)。これらの研究により、シェディング現象の一つの経路としてエクリン汗腺を介する可能性が想定される。しかしながら、体温を下げるために汗を利用する哺乳類はヒト以外ではウマのみであり、本来マウスは汗をかかない。そのため、個体間伝播がヒト特有の経路だけによるものであるならば、個体間伝播の存在をマウス実験のみで否定することは不可能であるが、このことはプレプリント内で一切議論されていない。
「無い」ことを証明するために
一般論として、「何かが存在しない」ということを証明するのは非常に困難であり「悪魔の証明」とも呼ばれる。そのためその現象が「無い」ということを主張するには、十分に工夫された膨大な量の実験を遂行した上で、「これほどの条件であっても結果として検出できなかった」と考察するのが通常の科学者としての研究姿勢である。しかしながら、そのような試行錯誤の痕跡は当該プレプリントにおいて見出すことができなかった。
新田氏らは「感染性を持ち深刻な健康問題を引き起こすという理論は、現時点の証拠に基づいて否定できる」、「自己増幅型RNAワクチンが複製し個人間で拡散するという仮説を評価するため動物実験を実施したが、我々の知見はこの理論を強く否定するものである」とも述べているが、上記の理由によりこれは事実ではなく、そのような記述を支持する実験結果は全く示されていない。
投与量と観察期間は適切なのか
また、使用されたレプリコンワクチンの量が適切であるかどうかも疑問である。そもそも適切な量を確認するためのコントロール実験が無いため、この実験自体が適切な条件で行われたという保証がない。仮に極微量のレプリコンワクチンが個体間伝播した場合、受け取った側のマウスの体内でレプリコンワクチンが増殖するまでにはタイムラグがあり、その後、抗原刺激を受けてから特異的IgGが産生されるまでには2〜3週間程度の期間が必要である。さらにレプリコンワクチンが個体間伝播した場合、数ヶ月後以降に抗体産生が生じる可能性を否定できない。よってわずか4週間程度の観察期間とは全く不十分なものである。
適切な実験に必要なこと
mRNAまたはスパイクタンパクの検出限界は解析手段によって大きく異なる。いわゆるmRNAコロナワクチンにおけるシェディングとは、現時点では機序が明らかになっていない現象であり、解析するにはその現象を検出する実験系を立ち上げる必要がある。またこのプレプリントでは抗体濃度の絶対値が記載されておらず、絶対値としての抗体価を判断できない。また著者らはレプリコンワクチンの定量を血清とリンパ節のみで行おうとしているが、その手法ではワクチンがいずれかの臓器で取り込まれ複製されていても検出の対象外となる。したがって、レプリコンワクチンが解析期間の後に循環系に復帰する可能性を否定できない。
(4) 蛍光光度計のDNA測定におけるRNAの干渉は既知である
qPCRとはDNAの混合物の中から特定の遺伝子配列を定量するための技術であり、DNAの総量を測定する目的には適さない。先行研究でもqPCRは汚染DNA量を過小評価する手法であることは指摘されている。PCR技術を用いて特定の配列を増幅した結果得られるDNA断片は「アンプリコン」と呼ばれるが、qPCRではアンプリコン未満のサイズのDNAは検出の対象外となる。しかしながら新田氏らの用いたアンプリコンのサイズは先行研究より大きく (Speicher, Rose et al. 2025)、この方法ではDNA量をさらに過小評価することになる。にも関わらず、新田氏らのプレプリントにはRNA作成の鋳型に用いたDNA量、アンプリコンの位置や実験デザインの目的や意図などの検出系の詳細や意図が記載されていない。RNase処理で蛍光光度計の測定値が変化することはMcKernan氏らの研究で既に報告されており (Speicher, Rose et al. 2025)、既知の現象である。
科学の大前提として「質の低い実験によって質の高い実験の結果を覆すことはできない」。しかしながら新田氏らは検証実験においてmRNAワクチンに使用されたメチルシュードウリジン修飾RNAを使用せず、ワクチンバイアル由来の汚染DNAの定量も一切行っていない。このように先行研究を上回る実験結果を何ら示していないにも関わらず、先行研究を一方的に否定している。
また新田氏らは「サンプル中のRNAをRNase Aで分解し、生成したオリゴ (モノ) ヌクレオチドを除去し、残存DNAを精製してから測定する必要がある。これまで、このような方法を用いた測定は報告されていない。」とも述べているが、精製の際のロスが汚染DNA量の過小評価に繋がる問題点に関しては既に先行研究で指摘されている (Speicher, Rose et al. 2025)。

 表1 世界におけるmRNAワクチンのDNA汚染の検証。Hulscher et al. 2025より転載。
表1 世界におけるmRNAワクチンのDNA汚染の検証。Hulscher et al. 2025より転載。
2025年10月現在において、コロナワクチンのDNA汚染が世界的に検証され、多くの科学者達の間で問題視されている。しかしながら、その中でただ一人だけ突出して極端に低い測定値を提示しているのが表1中の緑で示されている新田氏である (Hulscher, Bowden et al. 2025)。
McKernan氏らの先行研究では、汚染DNAがLNP(脂質ナノ粒子) に包まれている危険性を指摘しているが (Speicher, Rose et al. 2025)、新田氏らのプレプリントにおいては、コロナワクチンがLNPに包まれている件については完全に無視されており、その条件を加えた上での危険性を否定できる実験結果を何ら提示していない。
(5) 新田氏らの主張とは、トランスフェクトされたDNAの高頻度のゲノム組込みを検出しながらも人体への危険性を軽視するものである
当該プレプリントにはDNAがゲノム統合を起こした細胞を濃縮するような手順もなく、網羅的ゲノム解析も行われていないため、新田氏らの実験系ではゲノム統合を効率良く検出することは不可能であるが、このように感度の低い検証系にも関わらず、新田氏らは「2%の細胞のゲノムにDNAが取り込まれた」ことを報告している。これはすなわち、37兆の細胞からなる人体の2%の細胞のゲノムに外来DNAが取り込まれた場合、7400億もの細胞でゲノムの改変が起こるということを意味する。
さらに新田氏らは「正常な初代細胞では、ゲノム組み込み効率はおそらく数桁低い」と主張するが、その根拠については何ら示されていない。また、正常な初代細胞は個体を構成する多様な細胞を代表しているわけではない。細胞のタイプにより外来DNAの細胞内導入効率、ゲノム統合効率は異なるが、その機序自体には未だ不明な部分も多く、実際に全ての細胞種のゲノム組み込み効率が低いかどうかに関しては未知である。
その上、新田氏らは「生理的条件下では、1細胞に10万個の異物DNA分子を導入することは極めて起こりえない」「たとえ規制上限値 (10 ng/回) までのDNA汚染が存在しても、単一LNPに含まれるDNA分子は1〜10分子程度と考えられる」とも主張している。これに関しては、先行研究によってコロナワクチン汚染DNAの数は投与量あたり100億分子にも及ぶ可能性が指摘されている (Speicher, Rose et al. 2025)。さらに新田氏らの実験では、癌細胞に類似した細胞株HEK293を使用しているが、その手段ではDNA統合による細胞の癌化は検証できず、実際そのような検証はプレプリント内でも行われていない。
(6) 最後に
最終的に新田氏らは「mRNAワクチン製剤中のDNA汚染がDNA断片のゲノムへの組み込みを引き起こし、遺伝子機能や発現を変化させて様々な有害事象を誘発するという主張についても検証した。この理論も我々の結果によって否定された。」と断定しているが、上記の理由によりこれは事実ではない。もし仮に新田氏らの理論に基づくならば、培養細胞における外来DNAのゲノム統合の頻度がさらに高くとも正常な初代細胞 (これとてヒト個体を構成している多様な細胞を代表しているわけではない) ではゲノム組み込み効率が数桁低く、有害事象を誘発しないということになるが、それならば、そもそも著者らが培養細胞を用いた実験を行ったこと自体が無意味なものになる。
DNAのゲノムへの統合とはすなわち遺伝情報の書き換えであり、細胞癌化や癌の悪性化、次世代への遺伝子改変といった深刻な問題に繋がり得る重大な懸念事項である。それにも関わらず新田氏らは、これほどまでに高い効率でのゲノム組込みに対してさえも「問題はない」と断言している。基本的にワクチンとは健康な人を対象としたものであり、その潜在的マーケットは巨大である。また場合によっては膨大な人数にほぼ義務化すら可能なために、本来は極めて高い安全性が要求されるはずである。そのことを含めた上で、改めて新田氏らの主張とは「mRNAワクチン中の残留DNA断片がゲノムに組み込まれ、遺伝子機能や発現を変化させる確率は極めて低く、ワクチン接種者で報告されている様々な有害事象の考え得る原因となる可能性は低い」というものである。つまりこの主張とは、不十分な根拠をもってmRNAワクチンの持つ潜在的なリスクを矮小化し、その危険性を極端に軽視するものである。
また著者らは当該プレプリントにおいて、衆議院議員の原口一博氏および、かつてMIT (マサチューセッツ工科大学) でゲノム解析研究に従事し、現在はMedicinal Genomics社の最高戦略責任者 (CSO) であるKevin McKernan氏を名指しで批判している。そのため特にこのプレプリントはMeiji Seika ファルマ社が原口氏を対象とする現在進行中の裁判において、判断材料として利用される恐れがある。
以上のように、新田氏らのプレプリントはその質に関して非常に疑問点の多い内容にも関わらず、レプリコンワクチンを含めた次世代mRNA製剤の危険性を払拭しようと試みる製薬会社の根拠資料として利用されかねない内容であるため、これに対し看過できないと判断し、当該プレプリントの問題を指摘し異議を唱え反論した。
願わくは筆者らが、我々の見解を真摯に受け止め、科学者としての基本的なモラルに立ち帰った行動を取ることを望む。なぜならば、彼らの今後の動向いかんによっては、一般の方の科学者に対する信頼を大きく損なう事態も考えられるからである。筆者らには賢明な判断を求めたい。
References
Hulscher, N., M. T. Bowden and P. A. McCullough (2025). "Review: Calls for Market Removal of COVID19 Vaccines Intensify as Risks Far Outweigh Theoretical Benefits." Science, Public Health Policy, and the Law 6 :2019 2025.
Nitta, T., T. Kashiyama, Y. Matsumoto, T. Toyoda, T. Miyazawa, Y. Kamijima and K. Hideki (2025). "Verification of questionable information about the COVID 19 vaccines." JXiv preprint
Peters, S. E., J. Newman, H. Ray, J. A. Thorp, T. Parotto, B. Hooker, D. McDyer, L. Murphy, R. B. Stricker, M.McDonnell, P. J. Mills, W. Gieck and C. Northrup (2024). "Menstrual Abnormalities Strongly Associated with Proximity to COVID 19 Vaccinated Individuals." International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research 3 (2): 1435 1461.
Sano, S., M. Yamamoto, R. Kamijima and H. Sano (2024). "SARS CoV 2 spike protein found in the acrosyringium and eccrine gland of repetitive miliaria like lesions in a woman following mRNA vaccination." J Dermatol 51 (9): e293 e295.
Speicher, D. J., J. Rose and K. McKernan(2025). "Quantification of residual plasmid DNA and SV40 promoter enhancer sequences in Pfizer/BioNTech and Moderna modRNA COVID 19 vaccines from Ontario, Canada."Autoimmunity 58 (1):